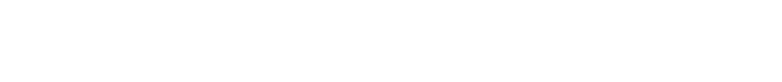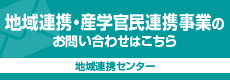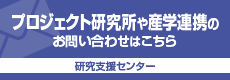学内公募研究(令和7年度)
令和元年度より、本学の研究推進と研究のブランド化推進のため、本学教員の提案による研究テーマを公募し、審査委員会にて内容を審査後予算措置し支援しております。
研究タイプは、
「萌芽型」(科研費等競争的資金研究を目指す研究)
「発展型」(現在実施しているの競争的資金研究をさらに発展させる研究)
「実用化型」(企業との産学共同研究の準備段階の研究)
「地域連携型」(自治体・地域団体等との地域連携事業の準備段階の研究)
となっています。
- 単一電子の遠赤外光による制御と機能性素子への応用
- パウダージェットデポジション法による高温超伝導製膜の最適化
- 脳スライス活動計測法の検討
- 可搬型高パルス出力テラヘルツ波パラメトリック光源に向けた励起レーザーの小型化
- バーチャールリアリテイを用いた没入型学習支援システムの開発に関する研究
- 橋梁におけるひずみ変化量の簡易的計測手法の開発
- 石材を用いた堤防裏法の越流浸食対策に関する研究
- リニアジェネレータを利用した木造用セミアクティブ制振装置の開発
- 認知症当事者の声を反映させた環境評価ツールの開発
- 生体ガス測定デバイスを用いた睡眠時無呼吸症候群の重症度評価基準の開発
- 人の指構造を模倣した多感覚センサ搭載ロボットハンドの作製と自然な操作方法の研究開発
- 小型装置を用いた呼気VOC成分の分離分析法の研究開発
- アルカリ水溶液を利用して発火リスクを無効化するリチウムイオン二次電池回収装置の開発
- 歯科用レーザー光源の開発
- 原位置繰り返しプレッシャーメーター試験手法開発及び現場実証実験
- 動物園の資源循環に着目した持続可能社会モデルの構築と環境学習プログラムの制作
- 商店街空間における自転車走行空間整備に関する基礎的調査研究
- 「令和7年度アートの町『新地』創造・アートの魅力発信事業共同研究 ―バーチャルミュージアム構築に関する共同制作―」
- 地域連携活動の発信方法とドキュメンテーションに関する研究
- 空き家等とその対策に関する意識と課題 ―所有する住宅の将来をどう考えるか―
単一電子の遠赤外光による制御と機能性素子への応用
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 電気電子工学課程 教授 柴田 憲治
パウダージェットデポジション法による高温超伝導製膜の最適化
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 電気電子工学課程 教授 新井 敏一
脳スライス活動計測法の検討
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 電気電子工学課程 教授 鈴木 郁郎
可搬型高パルス出力テラヘルツ波パラメトリック光源に向けた励起レーザーの小型化
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 情報通信工学課程 准教授 縄田 耕二
バーチャールリアリテイを用いた没入型学習支援システムの開発に関する研究
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 情報通信工学課程 講師 グエンヴァンドゥック
橋梁におけるひずみ変化量の簡易的計測手法の開発
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 都市工学課程 教授 小出 英夫
石材を用いた堤防裏法の越流浸食対策に関する研究
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 都市工学課程 准教授 菅原 景一
リニアジェネレータを利用した木造用セミアクティブ制振装置の開発
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 建築学科 講師 畑中 友
認知症当事者の声を反映させた環境評価ツールの開発
- 研究タイプ
- 萌芽型
- 研究代表者
- 生活デザイン学科 准教授 谷本 裕香子
生体ガス測定デバイスを用いた睡眠時無呼吸症候群の重症度評価基準の開発
- 研究タイプ
- 発展型
- 研究代表者
- 電気電子工学課程 教授 辛島 彰洋
人の指構造を模倣した多感覚センサ搭載ロボットハンドの作製と自然な操作方法の研究開発
- 研究タイプ
- 発展型
- 研究代表者
- 電気電子工学課程 教授 室山 真徳
小型装置を用いた呼気VOC成分の分離分析法の研究開発
- 研究タイプ
- 発展型
- 研究代表者
- 環境応用化学課程 教授 丸尾 容子
アルカリ水溶液を利用して発火リスクを無効化するリチウムイオン二次電池回収装置の開発
- 研究タイプ
- 実用化型
- 研究代表者
- 電気電子工学課程 教授 下位 法弘
歯科用レーザー光源の開発
- 研究タイプ
- 実用化型
- 研究代表者
- 情報通信工学課程 教授 佐藤 篤
原位置繰り返しプレッシャーメーター試験手法開発及び現場実証実験
- 研究タイプ
- 実用化型
- 研究代表者
- 都市工学課程 教授 権 永哲
動物園の資源循環に着目した持続可能社会モデルの構築と環境学習プログラムの制作
- 研究タイプ
- 地域連携型
- 研究代表者
- 都市工学課程 准教授 北條 俊昌
商店街空間における自転車走行空間整備に関する基礎的調査研究
- 研究タイプ
- 地域連携型
- 研究代表者
- 都市工学課程 准教授 泊 尚志
「令和7年度アートの町『新地』創造・アートの魅力発信事業共同研究 ―バーチャルミュージアム構築に関する共同制作―」
- 研究タイプ
- 地域連携型
- 研究代表者
- 産業デザイン学科 教授 堀江 政広
地域連携活動の発信方法とドキュメンテーションに関する研究
- 研究タイプ
- 地域連携型
- 研究代表者
- 産業デザイン学科 講師 坂川 侑希
空き家等とその対策に関する意識と課題 ―所有する住宅の将来をどう考えるか―
- 研究タイプ
- 地域連携型
- 研究代表者
- 生活デザイン学科 准教授 伊藤 美由紀
過去アーカイブ
本学教員の研究シーズの社会実装を推進するため、企業との共同研究、自治体との共同事業に資金を確保し推進しております。プロジェクト研究事業は、本学教員が代表となり、地域企業と共同による実用化の試験と開発を目指す事業です。
以下の研究タイプのプロジェクト研究事業を実施しております。
プロジェクト研究一覧
共同プロジェクト研究(実用化型)研究支援センター(RSC)
- 実用化開発研究
- 実用化の可能性がすでに示されていること。実用化の可能性から、その後の実現を目指す開発研究。
- 実用化試験研究
- 基盤研究を終了していること。基盤研究後の実用化の可能性を一層明らかにするための開発研究。
地域連携プロジェクト研究地域連携センター(CRC)
地域の発展に寄与することを目的とした調査又は研究。
主に対象となる地域と連携し、地域文化・地域産業・人材育成等に関わる研究推進を図る事業です。フィールド調査、地域産業や自治体との連携を図りながら進めます。
その他プロジェクト研究
せんだい創生プロジェクト地域連携センター(CRC)
せんだい創生COCプロジェクト
「地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)」の地域志向教育として「地域」を志向した「仙台市のまちづくり」や「地下鉄東西線沿線に関わるまちづくり」をテーマに、学生参画によるプロジェクト研究活動を実施しております。
せんだい創生プロジェクト
仙台市と東北工業大学とのまちづくりにおける連携・協力に関する協定に基づき、市民活動の活性化や市民交流の向上、地域社会の発展と未来を担う人材育成などを目的に、まちづくりプロジェクトの企画及び運営を行うものです。
※本プロジェクトでは、仙台市の課題を以下の4分野に分類し、研究活動を実践しております。
研究分野
- 福祉・高齢者
- 防災減災・まちづくり
- 環境・持続可能性構築社会
- 公共交通